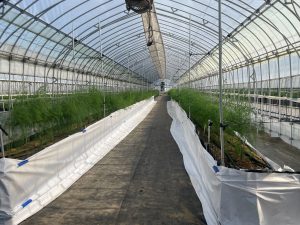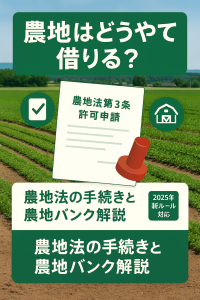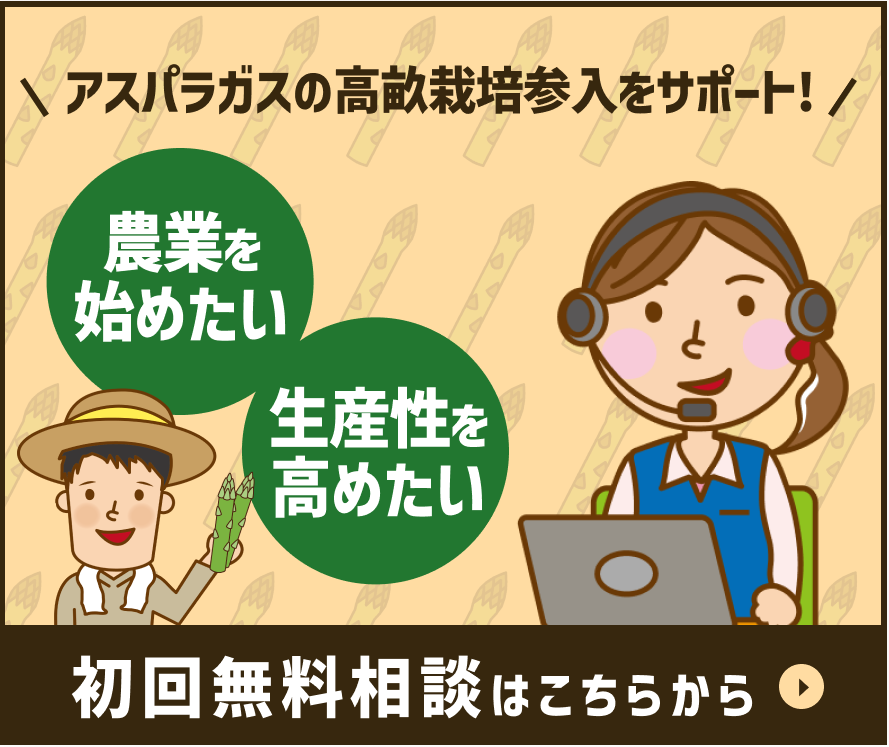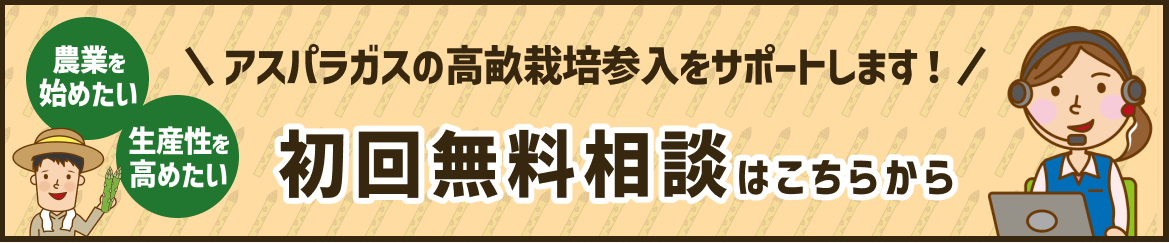はじめに
サラダや炒め物で使用されることが多いアスパラガス。
特有の食感や味わいが好きという声をよく耳にします。
しかし、食べたことはあってもどのような野菜なのかご存じない方も多いのではないでしょうか?
本記事では、そんなアスパラガスの基本知識を栽培者目線でご紹介します!
アスパラガスの歴史について詳しく知りたい!という方はこちらの記事をご覧ください。
→こちら
2. アスパラガスの基本知識
それでは、早速アスパラガスについて学んでいきましょう!
① アスパラガスの基本情報
学名はAsparagus officinalis L. です。
以前、分類はユリ科に属していましたが、今ではDNAによって決定されるAPG分類ではキジカクシ科に属しています。
原産地は南ヨーロッパで古代ギリシャやローマ時代には、すでに野生のアスパラガスが食べられていたとされています。
② アスパラガスの生態と特性
アスパラガスはユリ科の多年草で、私たちが普段食べているのは新芽の部分です。地下茎が年々育っていき、貯蔵根に蓄積された養分を使って春先にニョキニョキ芽が伸びる仕組みです。気温が上がると、あっという間に伸びてしまうのが特徴です。とくに春のピーク時には、一晩で数センチ伸びることも珍しくありません。「いまが収穫ベスト!」というタイミングを掴みやすいともいえます。
収穫が終わったら、今度は生えた茎葉でしっかり光合成をして貯蔵根に栄養を蓄え、翌年の生長に備えます。無理に収穫しすぎると、翌年の株が弱ってしまうこともあります。多年生だからこそ、適度な休養を与えることがポイントです。アスパラガスは意外とデリケートです。ここを踏まえて栽培計画を立てないと、持続的な収量アップは難しくなります。
③ 多年生作物としてのメリット・デメリット
多年生作物であることのメリットは、長期的な視野で安定収穫を目指しやすいことです。毎年植え替える手間がないので、その分コストや労力を抑えられます。
一方で多年生作物であることのデメリットは、初期投資が高く、植えてから2年くらいは思うように収穫できない時期が続くことです。資金繰りが苦しい方には少しハードルが高いかもしれません。また、長く同じ場所で育てるため、もし病害虫が発生すると被害が広域的かつ長期的になるリスクがあります。さらに朝早くの作業が必須になる収穫時期は、朝が苦手という方にとっては少々キツい可能性があります。
④アスパラガスの種類
グリーンアスパラガス
「グリーンアスパラガス」は地面より上に伸びた若い緑色の茎を収穫したものです!
日光をたっぷり浴びることで生じるクロロフィルが鮮やかな緑色を生み出し、シャキッとした歯ごたえと爽やかな風味が楽しめるのが特徴です。ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれ、疲労回復に役立つアスパラギン酸や抗酸化作用をもつグルタチオンなども含まれています。
ホワイトアスパラガス
ホワイトアスパラガスは、もともとグリーンアスパラガスと同じ品種ですが、栽培中に土を寄せたり遮光したりして日光を遮ることで、光合成が行われずに白色のまま成長します。グリーンアスパラガスに比べて、ほろ苦さやほのかな甘みを含んだ上品な風味が特徴です。
紫アスパラガス
紫アスパラガスは、表皮にポリフェノールの一種である「アントシアニン」を豊富に含む、珍しい紫色の品種です。グリーンアスパラガスよりもやや甘みが強く、繊維が柔らかいため、シャキッとした歯ざわりを残しやすく、食べやすい点が魅力です!
⑤ 収穫サイクル
アスパラガスの収穫は主に春先がメインシーズンです。昼夜の温度差が大きいほど甘みが増すため、この時期には「朝採れ」というキーワードが非常に魅力的に映ります。秋頃まで収穫はできますが、収量は春ほどではないため、あくまで「ボーナス的」な位置づけになります。
ただし、鮮度を重視するあまり、収穫から出荷までの時間管理がシビアになるのは事実です。作業体制や人員配置、配送手段など、裏でしっかり計画しておく必要があります。
⑥ アスパラガスの販売
鮮度がそのまま美味しさにつながるアスパラガスは、飲食店や直売所で高く評価されます。とくに春のメインシーズンは「旬の国産アスパラ」として販売されることも多く、消費者の購買意欲も高まります。ここで「地元産」といった付加価値が重なったアスパラガスなどはさらに人気が高まります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
多年生作物であるアスパラガスは比較的省力化や収益化に向いている野菜と言えます。とはいえ、デリケートな一面も持っているので、栽培するときには病気などに注意が必要です。
これを機に、ぜひ調理だけでなく、栽培にもチャレンジしてみてください!
inaho株式会社では、アスパラガスの新しい栽培方法である高畝栽培の新規参入サポート支援も行っています!
まずは、初回無料相談へお越しください。